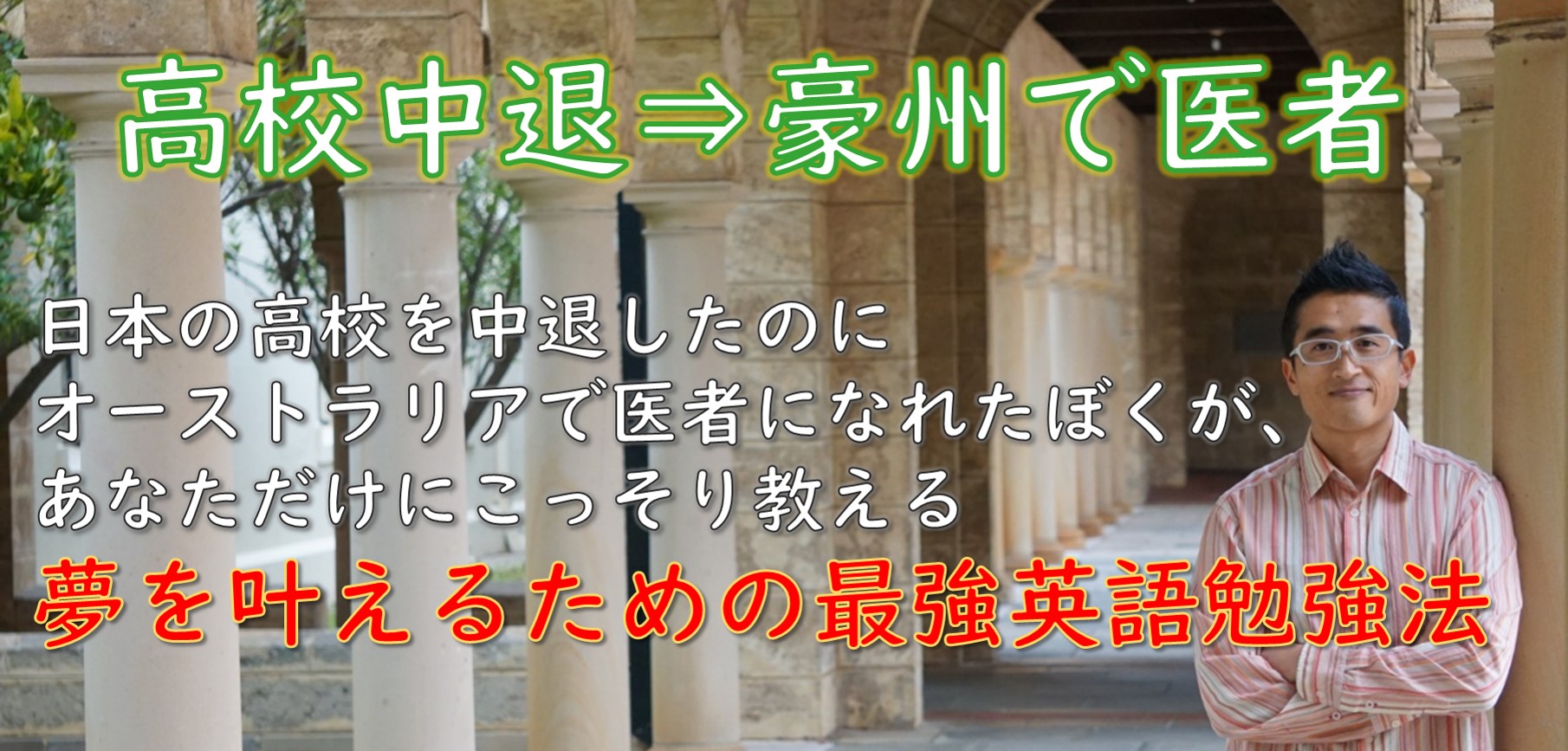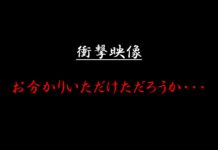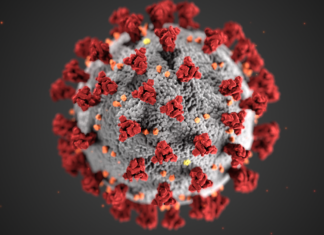翌日、朝の回診で再会した時、Aさんは泣いていなかった。Aさんは目をつぶっていて、ゆったりと夢の中を楽しんでいるように見えた。
ぼくは「Aさん、お早うございます。起こしてしまいすみません。」と声をかける。反応が無い。もっと大きい声で同じことを言う。反応が無い。ぼくは、同じぐらい大きな声を出しながら、Aさんの右肩をゆすった。Aさんが聞き取れない小さな声で何かを言う。Aさんの瞼は、かすかに動くだけで、その下にある青い目を見ることはできなかった。
ぼくは、患者さんノートを見直す。Aさんがウトウトするようになったのは、鎮痛剤の量を増やした前日からである。看護師さんが「痛みは軽減したが、Aさんの意識が朦朧とするようになり、これまでのような会話ができず、夕食も食べなかった」とノートに書き記していた。
インターン医師として働き始めたばかりのぼくは、「患者さんの痛みの緩和」のためのお薬が「意識朦朧状態」を引き起こしたことに罪悪感を強く感じた。もちろん、医学部でお薬の副作用を勉強するのでこのことは頭の中に入っている。しかし、薬の副作用が目の前の患者さんに実際に起きてしまうと、体験したものだけしかわからない感情が医師の中に生まれる。
ぼくは、一緒に回診をしていた先輩医師に「昨日増やした鎮痛薬が原因ですね。どれぐらい減らしますか」と聞いた。先輩医師は一言「Why not between the last and the current dose?」と言った。
ぼくは、朝に予定されていた鎮痛薬を投与しないことを看護師に伝え、看護師ノートに書かれている薬の量を増加前と増加後の間の量に書き替えた。
当日予定されていた Rizhotomy(脊椎椎間関節突起神経根切断術)は何の問題もなく行われた。手術を行った医師が手術後の痛みを考慮して、看護師ノートの鎮痛薬の量を、ぼくが最初に増量した量へと変更をしていた。
次の日の回診中、手術したところが少し痛いけど、背中の痛みと硬直はほぼなくなった、とAさんは言った。幸い、鎮痛薬の副作用はなく、理学療法士と作業療法士のカウンセリングを受けて、そのまま退院された。退院時の鎮痛剤は最低限のものだけが処方された。