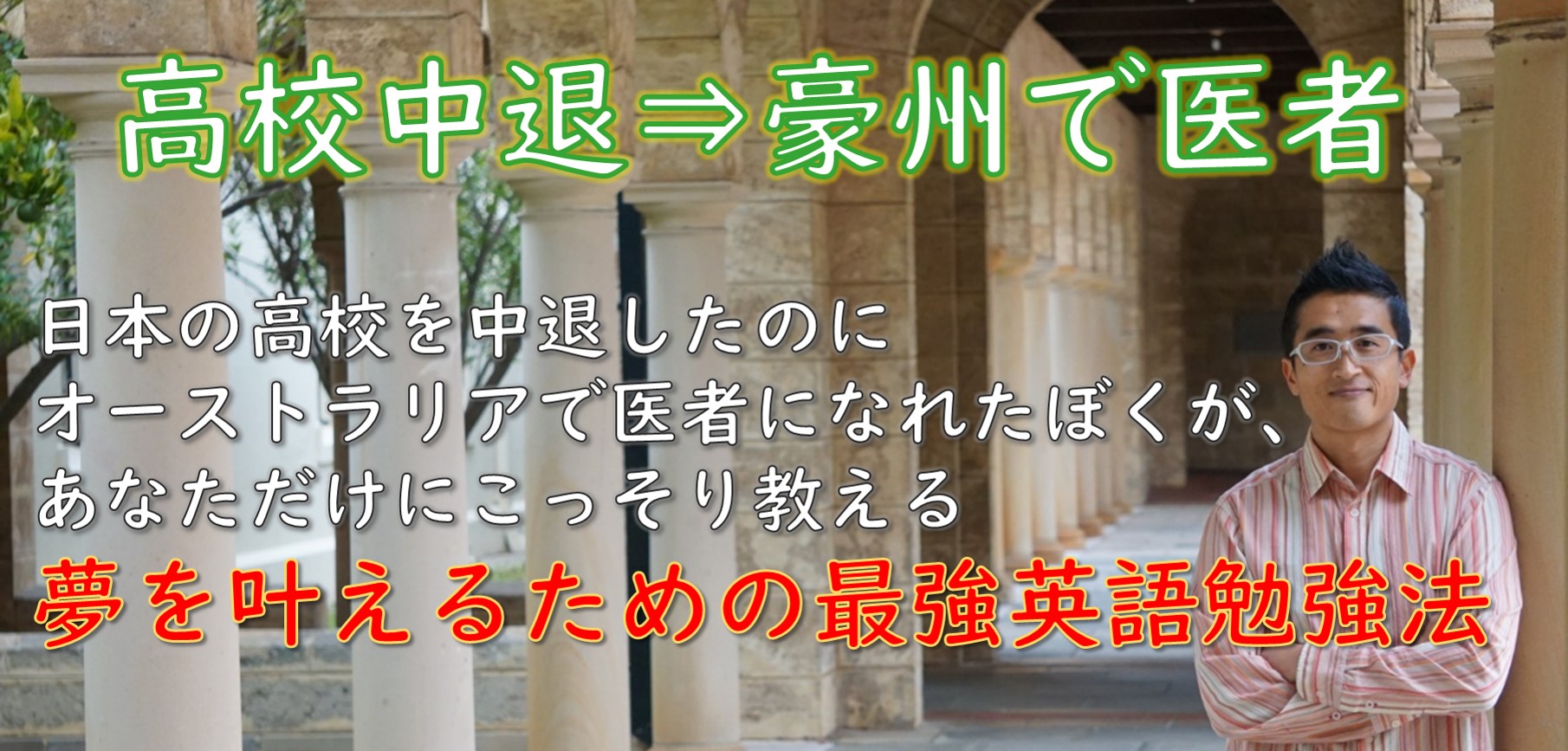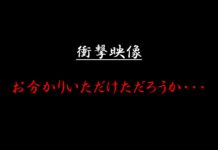ぼくが働いている Sir Charles Gairdner Hospital には、様々な専門科の医者が働いている。産婦人科と小児科、そして超ニィシュの専門科を除く全ての専門科が、Sir Charles Gairdner Hospital にある。
チャーリー(Sir Charles Gairdner Hospitalの愛称)はTeaching hospitalでもあるため、病院は24/7(24 hours, 7 days a week)医療行為を施している。しかし、医療従事者も人である。夜になれば、家に帰って、睡眠をとらなければならない。また、燃え尽き症候群にならないために、定期的に休みを取らなけれならない。専門家の先生が休んでいるとき、チャーリーは医療行為をストップするのか?答えは否。
夜になって専門医療チームが帰宅して眠っている(もしくは休日で休んでいる)間、Charlie’s After-hour Team (略してCAT)が、病棟にいる患者さんのケアに当たる。After-hourは文字通り、通常勤務時間外という意味である。しかし、通常勤務時間外チームだ名前がかっこ悪いので、ここではコードブルーチームと名づけることにする。(コードブルー、つまり医療緊急事態のこと。患者さんの顔が青ざめている状況を想像いただけたらいい)。
ぼくがコードブルーチームのレジデントをしているときは、合計で5人の医者(1人のレジストラ医師と4人のレジデント医師)が、精神科、集中治療室、救急科を除くすべての病棟の患者さんのケアをしていた。また、緊急外科手術は、専門の外科医が常に交代制で病院に待機していて、コードブルーチームが手術に参加することはない。
レジデントは、ひとフロアをそれぞれ担当していたので、レジデント医師一人当たり大体80名ほどの患者さんのケアに当たっていた計算になる。レジストラ医師はそのすべての患者さん(320名!)がケアの対象になる。もちろん、すべての患者さんのカルテに目を通すことは不可能である。そこで、病棟のナースがケアを必要としている患者さんを見つけ出し、仕事の難易度に応じて、タスクをレジデント医師(もしくはレジストラ医師)に振り分けていくのだ。
医師はポケベルを持っていて、そのポケベルに「○病棟のルーム何番で○○してください」という連絡が届く。また、それぞれの病棟に「やること一覧表」が置かれていて、その表を見ながら、優先度順に仕事をこなしていく。フロアごと、もしくは勤務日によって仕事量・種類が変わることがあり、レジデント医師はお互いを助けながら仕事をしていた。助け合うチームで働くことと、自分のことしかしないチームで働くことは、天と地ほどの差がある。
ぼくがAさんに出会ったのは、外科の病棟だった。ぼくは外科の病棟で患者さんの薬剤チャートを書き直していたのだが、若い看護師さんがぼくの背中をつついて「ヒロ、ちょっと来て」と声をかけてきた。ぼくは言われるままに、早足で歩く看護師さんの後を付いて行った。4人部屋の病室に入ると、別の看護師さんがAさんの右足太ももあたりに手を置いていた。看護師さんの手の間から赤い鮮血がゆっくりだが確実に流れ出していた。
ぼくはどこから出血しているのかを見るために、Aさんの脚を押さえていた看護師さんに「出血元をみたいので手を放してみてください」と言った。看護師さんが手を離したその瞬間、太い糸のような鮮血が天井に向かって放物線を描いた。放物線は定期的に大きくなったり小さくなったりした。
看護師さんは慌てて手を押さえ、「どうも尿道カテーテルが包帯の上から傷口に触っていたようなんです」と大粒の汗を額に書きながら言った。ぼくは「ありがとう。圧迫を続けてください」と看護師に伝え、ベッドそばにあるコードブルーのボタンを押した。真夜中に大きなサイレンが鳴った。
ぼくがコードブルーのボタンを押したのは医師になって2回目だった(1回目はパーキンソン病の患者さんの最高血圧が35だった時)。速くなった心臓の鼓動が鼓膜にまで聞こえてきた。ぼくは、ナースステーションで僕の背中をつついた患者さんにバイタルサインを計ることを支持した。そして、他のレジデント医師とレジストラ医師が来るまでに、Aさんに新しいIVカニューレ(18G)を挿入し、そこから血液を採取した。
他の医師たちが部屋に到着するのにかかった時間はものの1,2分のことだったのかもしれない。それでも、ぼくにとって1時間のようにも感じられた。「早く来てくれ。この責任からぼくを開放してくれ」と無意識に体が感じていたと思う。到着したチームに少し安心したぼくは状況(なぜコードブルーのボタンを押したのか)を伝えた。先輩のレジストラ医師がリーダーとなり、それぞれの役割分担がなされ、ぼくは第一発見者ということで、執刀医に連絡を取った。
Aさんは、真夜中のオペ室に送られていった。
ぼくの靴をふと見ると、Aさんの血液が黒く固まっていた。