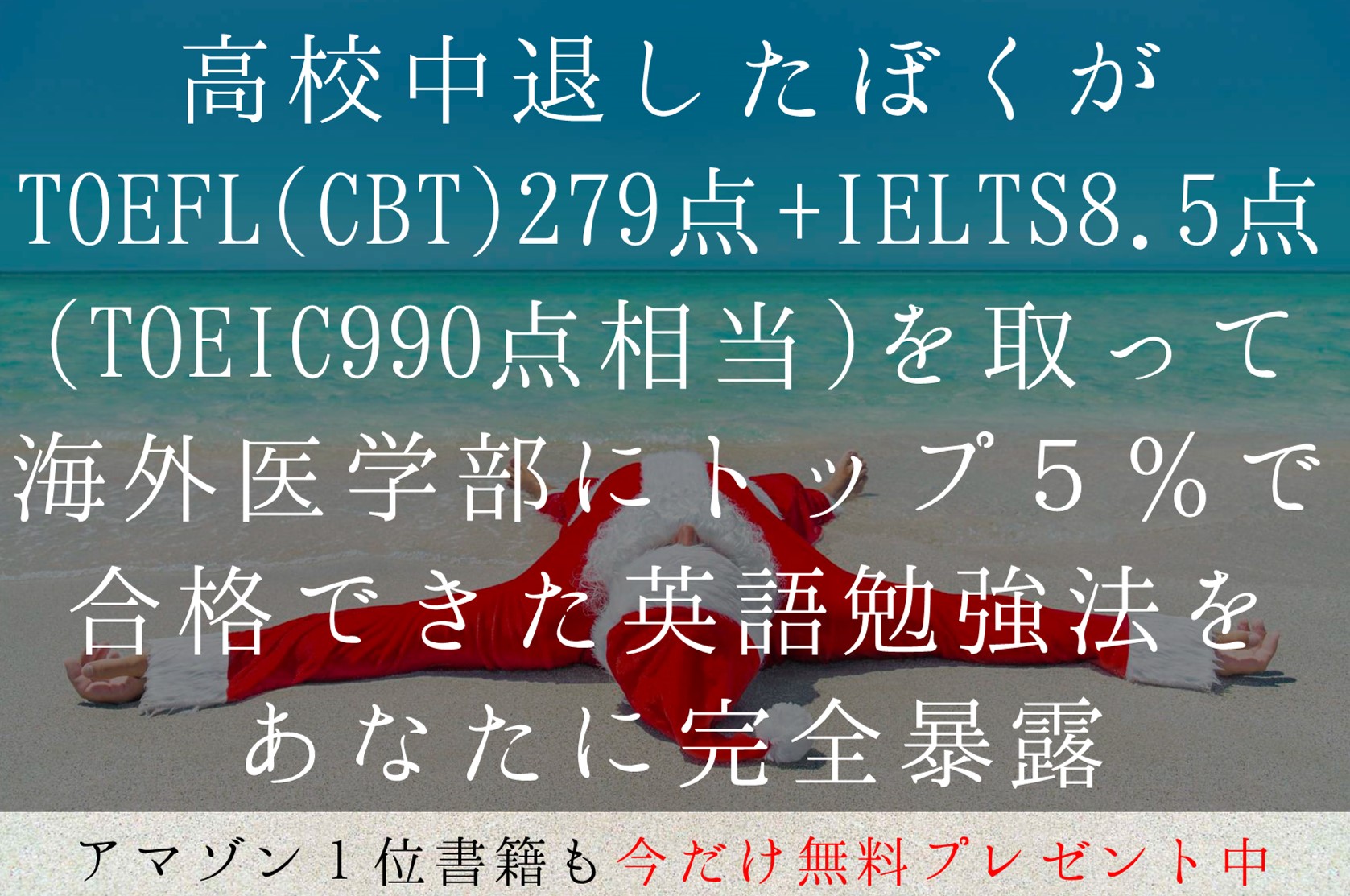オーストラリア医師、レジストラを振り返る(パート5:リハビリ科)
リハビリ科の話は過去の記事で触れたが、リハビリ科の患者さんのケアはなかなか一筋縄ではいかないことが多い。特に患者さんが年配になればなるほど、急性の医学的な問題だけでなく、慢性疾患や社会的な問題が大きな割合を占めることになる。
Aさんは、カナーボン出身の80代男性で先住民の方だった。Aさんは、脳発作のせいで左側の上半身と下半身が大幅に機能しなくなっていた。そのため、Aさんは車いすに乗って移動する訓練の必要があった。
Aさんはヘビースモーカーで、病院の外に行ってタバコをいつも吸いたがった。車いすをうまく使えないAさんをひとりで外に行かせることはできない。車いすから落下してけがをするかもしれないからだ。かといって、Aさんにそのことを話すと「おれはタバコを吸いたいんだ」といって右手にコップやフルーツなどを握って壁や病院のスタッフにめがけて投げたりした。そのときの形相は鬼のようなものだった。患者さんのわがままに答える必要はないと言う方もおられるかもしれないが、患者さんと医療スタッフの間に溝があると、リハビリはなかなか前進しないのだ。
Aさんのリハビリにはさらに大きな問題があった。Aさんのパートナーである奥さんは、末期腎機能の患者さんで血液透析を定期的に地元のカナーボンで受けなければいけなかった。しかし、Aさんのリハビリが長引くことがわかると、Aさんも奥さんも「パースで再会する」ことを望んだ。つまり、奥さんの血液透析をパースでも行えるように手続きをし、奥さんが滞在できる場所を用意する必要があった。
Aさんのリハビリにブレーキをかけたのはそれだけではなかった。前述したように、Aさんは先住民の方だ。先住民の文化で血縁以外の人も家族になる。そして、家族と称する人たちがたくさん病院に見舞いに来るのだ。すべての家族を一堂に会することができればいいのだが、往々にして自分たちの都合に会う日にAさんに会いに来る。そして、医師のぼくに「Aさんのリハビリの状況」「カナーボンに帰れる日」などを聞いてきた。おそらくだが、ぼくが家族会議と称して行ったミーティングの回数は2か月ほどの入院期間で50回を超えていたと思う。
ぼくは医師としての仕事以外にも、Aさんの銀行口座カードを再発行するための文書を用意したり、Aさんがあまりにタバコを吸いたくて暴れたとき、ぼくが自ら車いすを押して一緒に外に行ったりした。患者さんにタバコを吸うことを容認したぼくは医者失格なのかもしれない。でも、Aさんは80歳で脳発作のせいで左半身不随で思うように体を動かすこともできない。さらに、心のよりどころとなる奥さんは遠いところで待っている。鬱憤と不安が溜まっているAさんに寄り添うことができる唯一の糸口は、タバコしかなかったのだ。