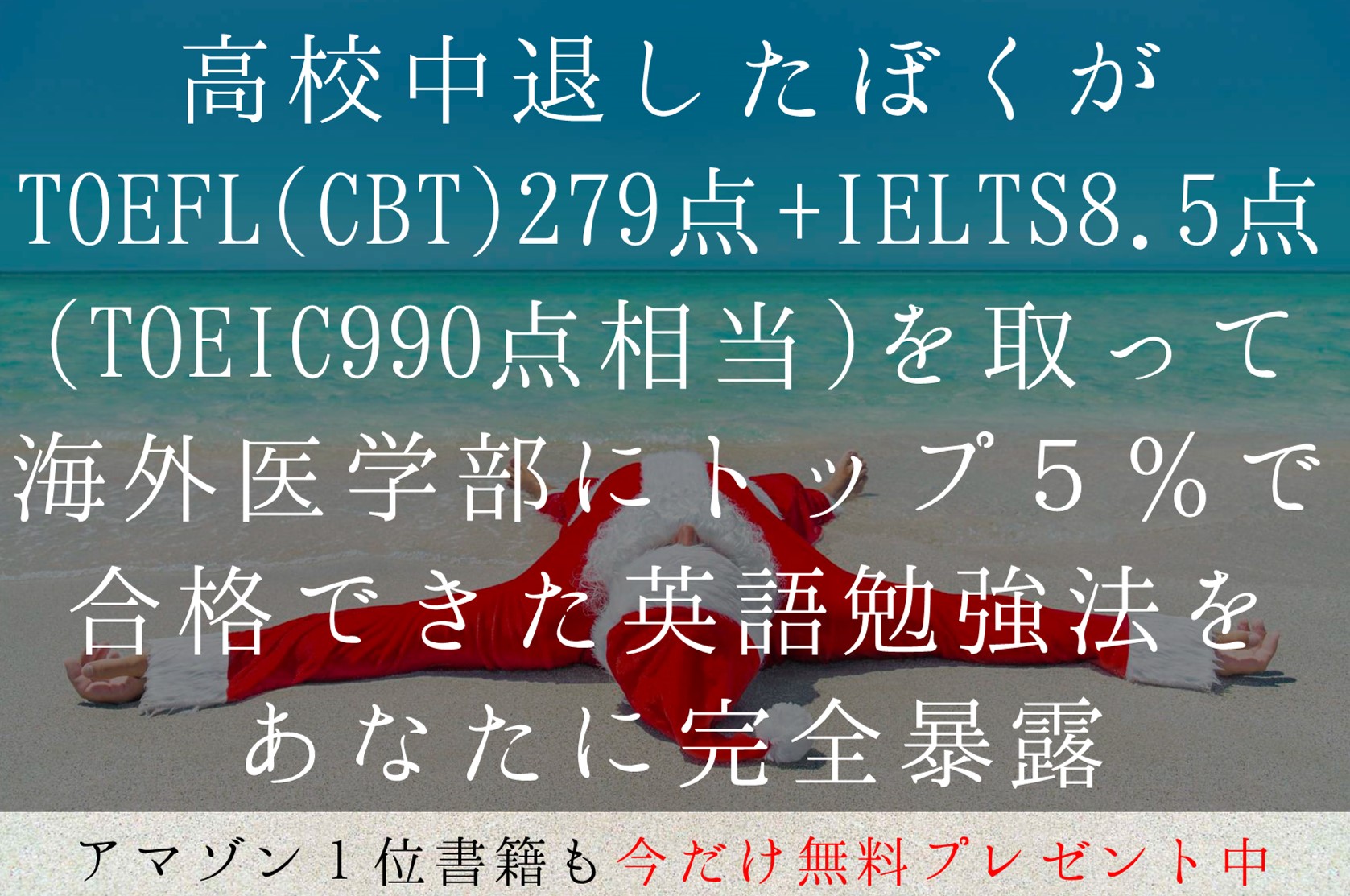ぼくが勤めている Sir Charles Gairdner Hospital には精神科がある。しかし、ぼくがレジデント医師として精神科のローテーションに回ったのは、Shenton Park という町にある Selby Lodge という精神科の病院だった。
Selby Lodge には、2つの精神科医チームがあり(各チーム1名のコンサルタント精神科医と1名の精神科レジストラ医師からなる)、各チームが患者さんの半数を担当し精神ケアに当たっている。Selby Lodge は一般的な精神病院とは少し違い、65歳以上の患者さんしか入院できない。そのため、大体の患者さんは、精神病以外にも、高年齢者によくみられる高血圧や糖尿病などの生活習慣病(もしくは向精神薬の副作用が原因によるメタボリック症候群)を患っている。そのため、Selby Lodgeで働くレジデント医師(ぼく)に期待される役割は、精神病のケアを精神科医チームから学びながら、精神病以外の病気のケアにも当たることである。

ぼくがAさんに出会ったのは、病棟の廊下である。Aさんは、糖尿病が原因による下腿切断で右脚を失っており、廊下と廊下をつなぐセキュリティのドアの端っこで車イスに座っていた。Aさんの近くには、コンサルタント精神科医、レジストラ医師、看護師マネージャー、そしてセキュリティ男性が2名が、2メートルほどの距離を置いて、Aさんを取り囲むように立っていた。
Aさんの話をよく聞いてみると、「病院の外で友だちが待っていて、その友だちと一緒に家に帰って、虐待を受けている娘を助けに行かなければならない。だから、この病院から出してくれ!」という趣旨のものだった。
ぼくがAさんのことをよく覚えているのは、Aさんの精神病でも下腿切断で失った右脚のことでもない。実は、Aさんが担当のコンサルタント精神科医を度を越して毛嫌いしていたことだった。精神状態が安定しているときのAさんはよく、ナースステーションのそばに車いすをつけて、ぼくを含む病院スタッフと一緒にありきたりの日常会話にふけっていた。Aさんから友だちや家族を大事にするような誇大妄想的な発言がよく聞かれたものの、スタッフのみんなは親しみを感じながら接していた。
しかし、Aさんの近くに担当のコンサルタント精神科医が来ると、Aさんの行動はまるで別人格に変わってしまったかのように豹変した。まず、Aさんは両手を車いすの車輪に載せて車いすを前後に揺らし、まるでコンサルタント精神科医をひき殺そう、というような行動をとった。そして、顔を真っ赤にしながら「俺はあんたのことを信用していない。俺のことを全く理解せずに治療に当たっているからだ」と半狂乱でよく叫んだ。
「俺はあんたのことを信用していない。俺のことを全く理解せずに治療に当たっているからだ」
専門分野にかかわらず、医者が患者さんにそんなことを言われたら、結構な精神的なダメージを受けるはずだ。いや、ダメージどころか「医者失格」の烙印を自分に押して医者を辞めてしまうかもしれない。
Aさんは Selby Lodge に1年半近く入院していて、その同じコンサルタント精神科医が精神ケアに当たっていた。コンサルタント精神科医のプライドを傷つけないように、1年半の入院期間にどんなことがあったのかを聞いてみたが、Aさんの態度が豹変してしまうようなことは起きていないという。
Aさんの機嫌がいい日に、こっそりと「なぜコンサルタント精神科医のことをそんなに毛嫌いするの?」と聞いてみたが、きっかけになるようなことはなにひとつ聞き出せなかった。Aさんはただただ「俺はあの精神科医を信用していない。俺のことを全く理解せずに治療に当たっているからだ」を繰り返すだけだった。
ぼくが Selby Lodge でのレジデント医師の仕事を終えたその日も、Aさんは廊下と廊下の間にあるセキュリティドアの前を陣取り、ンサルタント精神科医、レジストラ医師、看護師マネージャー、そしてセキュリティ男性2名に取り囲まれていた。そして、ぼくがそばのドアを開けて帰ろうとすると、「ヒロ、いままでありがとう。あんたにはまだ可能性がある。患者のことを理解して治療してくれ」と叫ぶように言われた。
「患者のことを理解して治療してくれ」
Aさん、ぼくは患者さんのことを理解して治療に当たれているだろうか?