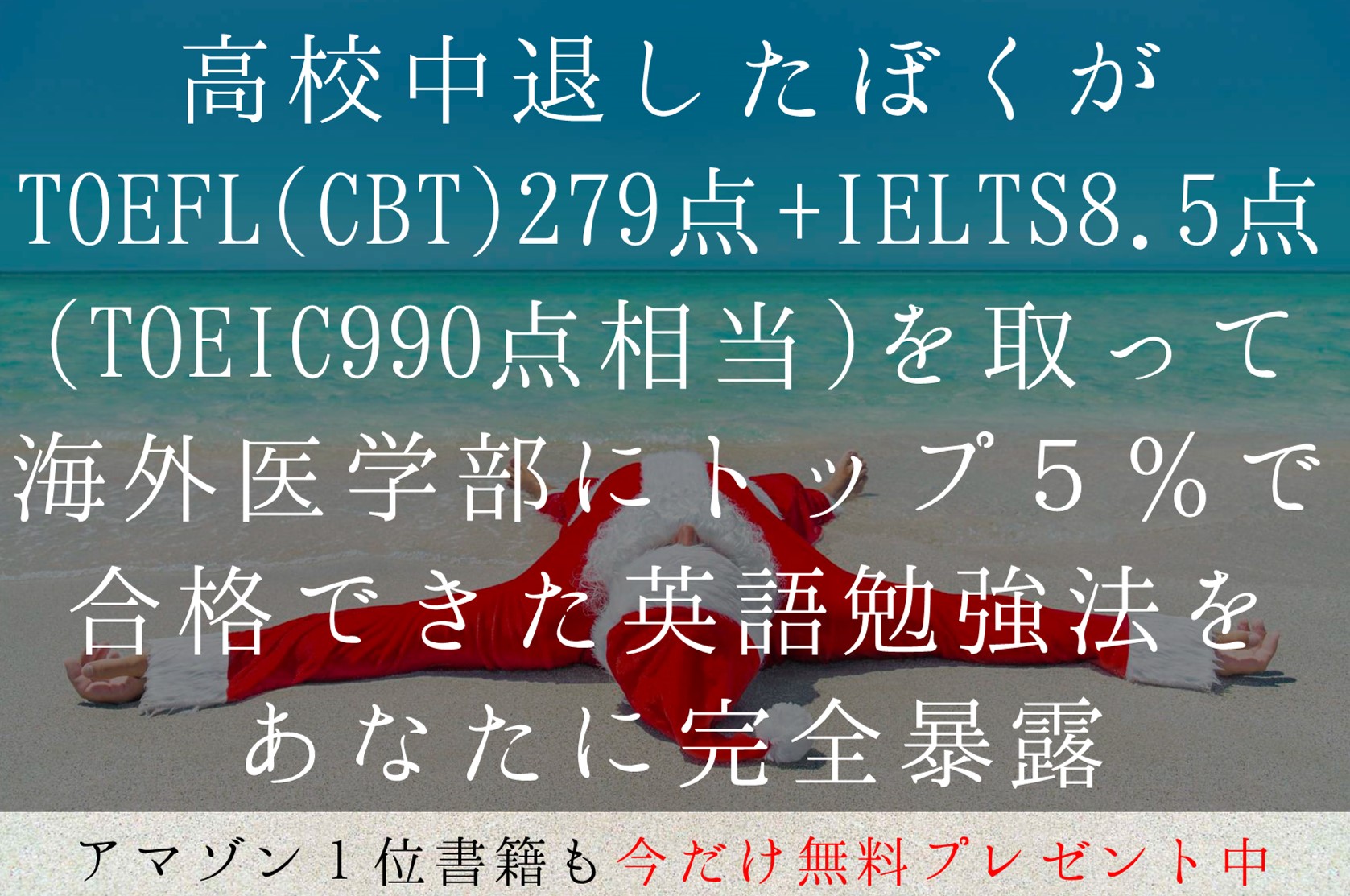Aさんが救急科に来た理由は、「体調がよくない」からだった。若干24歳のAさんのそばには、フィアンセの女性が座っていた。
全てのレジデント医師がそうするように、ぼくは History taking(history of complaint, past medical history, current medications, allergy, family history, social history)とPhysical examinationをおこなった。
Aさんの「体調がよくない」を正確に表すと「倦怠感」だった。過去2か月間、倦怠感が悪化していて普段の生活がままならない、のだという。そのほかにも、夜汗をかいたり、過去2か月で体重が6キロも減ったという。
Aさんの家庭事情はとても複雑だった。Aさんは幼少期から父親から家庭暴力を受けていた。そして、Aさんが16歳の時に、母親が拳銃で父親を撃ち殺した後、母親自ら首を吊る、という悲惨な現場を目のあたりにしていた。さらに、Aさんが18歳の時に結婚した女性は、その1年後に首を吊って自殺している。Aさんは精神科と心理カウンセリングを受けながら、過去の呪縛と闘いながら前に進もうと苦しみ藻掻いていた。救急科に一緒に来ていたフィアンセは、Aさんが通っていたカウンセリングセンターで働いている女性だった。
ぼくが身体検査をすると、その時の自分には予想もしていなかった異常があることが分かった。Aさんは、彼の左半分の世界が見えていないのだ。彼の両目はしっかりと開いている。ぼくが彼の右側半分に手を持ってきて、「何本の指が見えますか?」と聞くと、Aさんはしっかり「3本」「2本」と正確に答えることができた。しかし、ぼくが彼の左側に手を持ってきて「何本の指が見えますか?」と聞くと、「何も見えません」と答えた。「何も?」「指や手だけじゃなくて?」と聞くと、「はい」と答えた。
ぼくは、先輩のレジストラ医師にAさんの状態を伝え、脳のCTスキャンをオーダーした。

出典:Radiopedia
Aさんの視覚野には、医学生でもはっきりとわかるほどの腫瘍が確認できた。
ぼくは救急科のステーションからベッドの上でフィアンセと話をしているAさんを眺めながら、Aさんの壮絶な生い立ち、それでも前に進もうと藻掻いている姿を、再度自分の目に焼き付けた。そして、大きな深呼吸を2回して、Aさんのベッドの方へ足を運んだ。
先輩のレジストラ医師が「スキャンの結果は私が伝えるわ」と言ってくれたが、「いえ、ぼくが伝えます。」と答えた。ぼくがそう答えたのは、苦しみながらも前向きに生きようとしていたAさんに深い敬意を抱いていたからだ。救急科での短い時間ではあったが、Aさんは「ぼくの患者さん」だった。
ぼくは、Aさんの脳に腫瘍が見られ、これが目が見えないことの原因で、倦怠期、体重の減少、夜汗なども腫瘍と関連しているかもしれない、ということを、Aさんと彼のフィアンセにゆっくりと伝えた。言葉を失ったふたりに少しの時間を与え、ぼくはAさんとフィアンセに腫瘍科、脳外科、放射線科の先生と話をすることを伝えた。
腫瘍科、脳外科、放射線科の先生が救急科に来てAさんと話をしている間、ぼくは救急科の別の患者さんのケアに当たった。そして、Aさんは今回は入院する必要はないという決断が下された。
ぼくは、退院していくAさんの手を握り、「大丈夫。ぼくらができることは全てやるから」と伝えた。Aさんは、目に涙を浮かべながらフィアンセの女性と救急科のドアを出ていった。