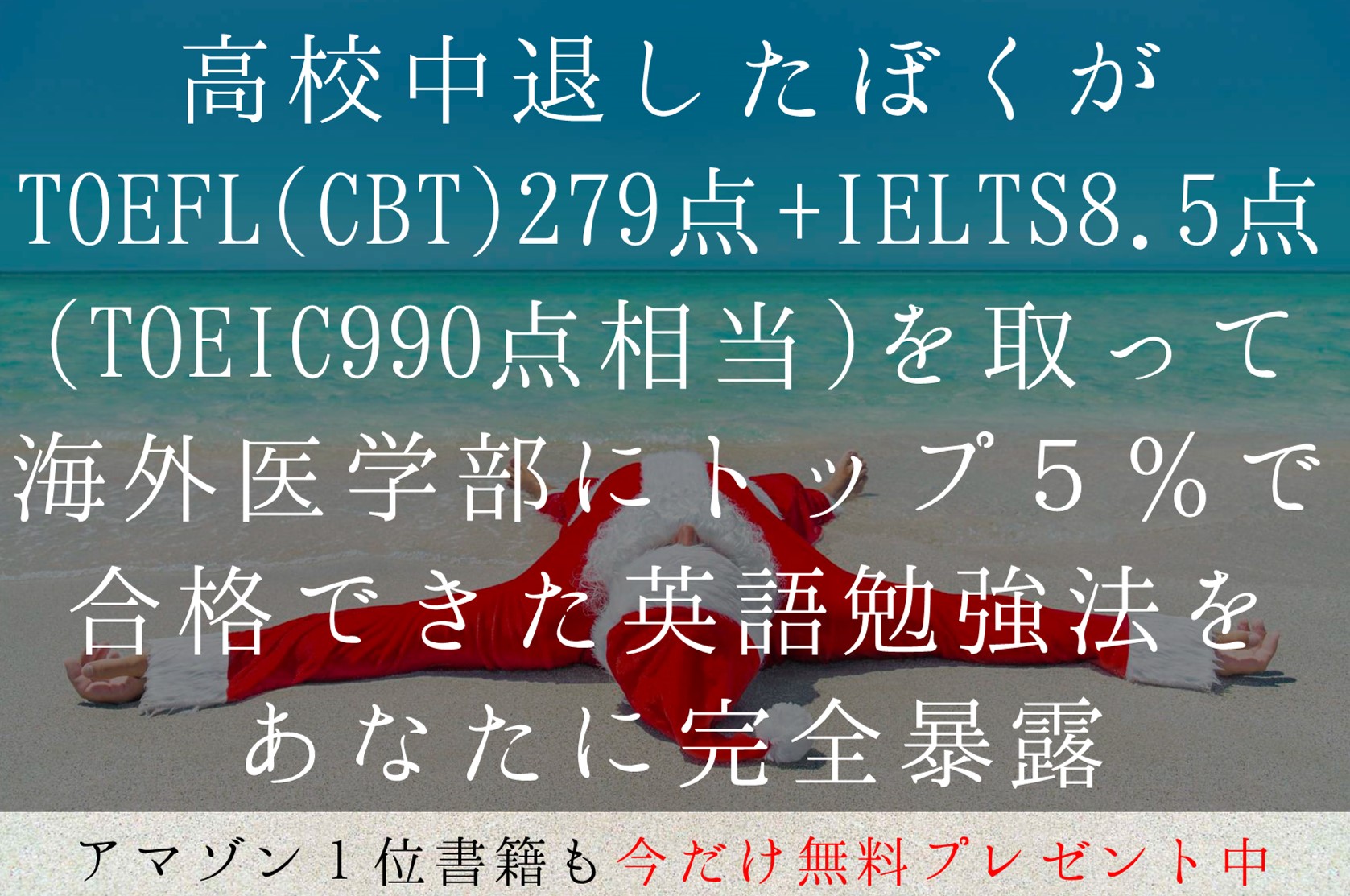急性疾患科は大変忙しい。専門科への入院は必要無いが退院できるほど容態は安定していない患者さんが、急性疾患科に入院する。その多くは、感染症や直腸出血などだが、原因不明の腹痛に苦しむ患者さんが来たり、医療的に不安定な拒食症の患者さんが来たり、緩和ケアの最適化が必要な末期がんの患者さんなども来た。
Aさんは20代の女性で、ブラジルからパースに語学留学に来ていた。ぼくは、Aさんに3週間ほど前に「下痢」で急性疾患科に入院していたときに出会っていた。便検査をすると、Campylobacterという細菌の存在が確認され、抗生物質投与後に退院したことを覚えていた。健康的で容姿端麗なAさんの魅力も記憶を助けてくれた。

出典:Pinterest
下痢は回復したものの、Aさんは再びSir Charle Gairdner Hospitalにやってきた。今度の症状は「全身の倦怠感」だった。救急科の医師は、Aさんがつい最近まで急性疾患科でケアを受けていた事実を確認したうえで、急性疾患科への入院を申請してきた。
しかし、ぼくがAさんを診るために救急科のベッドに行くと、数週間前に出会ったAさんとは何かが違うことを感じた。彼女は全身の倦怠感を訴えたが、慎重に身体検査を行うと彼女の下半身の顕著な弱さ明らかになった。話を聞くと、足>膝>腰の順に弱くなっていたことが分かった。
ぼくは、数週間前のCampylobacterの感染と、今回の下半身の麻痺を合わせて、Guillain-Barre Syndromeと診断し、急性疾患科ではなく神経科へ入院させるようにお願いをした。
Guillain-Barre Syndromeを診断した自分に多少の自尊心を覚えたが、その自尊心は数日後虚無となる。Guillain-Barre Syndromeの存在を示唆する神経伝導検査には問題はなかった。Aさんはその後、CT脳・脊髄を受け、Multiple Sclerosisを患っていることが分かった。