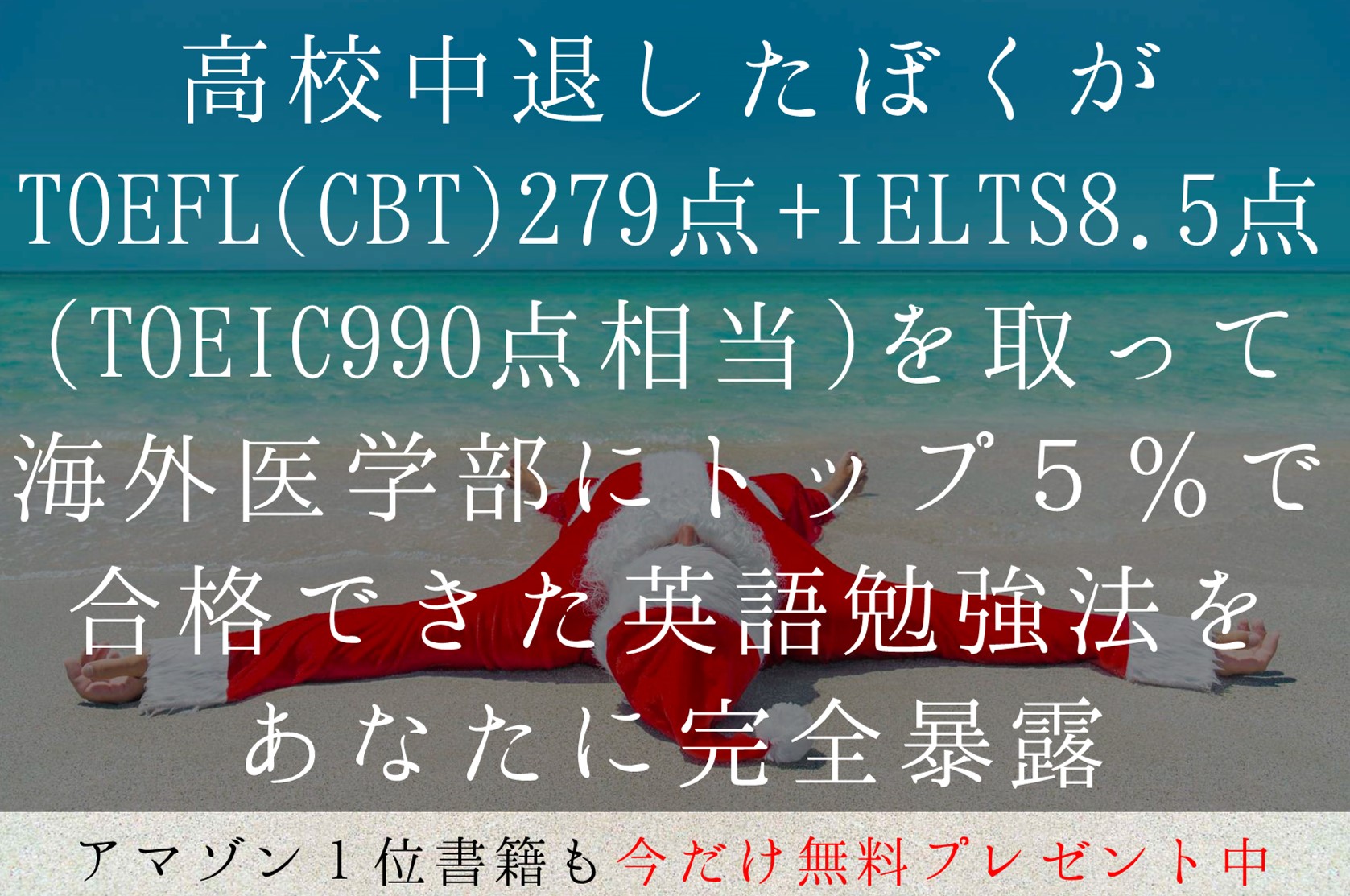オーストラリアの医師は、インターン、レジデント、レジストラという経験の梯子を登っていき、最終的には「どんな医師になるか?」という選択に迫られる。一般的に分かりやすい進路の選択は、外科なのか、内科なのか、精神科なのか、というところだろうか。
ぼくは小さいころから All thumbsと親に言われてきたこともあり、外科医には向いていないと漠然と思っていた。内科はどうかと言えば、同僚から「ヒロは内科医向き」と言われていたし、エビデンスを元に考えることが好きなほうなので、「内科に進むこともいいかな」と感じていた。精神科と言えば、自分が神経科学を専攻していたことや、精神科の先輩医師に「精神科に来ないか?推薦状を書いてあげるよ」と言われたこともあり、強い興味を持っている分野ではあった。
ぼくが進路を決められずに悶々と迷っている頃、世界はコロナウイルス(COVID-19)に怯えていた。ぼくはコロナウイルス病棟での勤務も経験したし、コロナウイルスに感染して亡くなられた方も診てきた。そんな経験もあり、感染症医の分野も面白そうだと思った。ただ、ひょんなことから、同僚から「現在、コロナウイルスのせいで総合医のプログラムに入るために必要な筆記試験が免除されている」という噂を聞いた。調べてみると、今回の受験まで筆記試験が免除される(つまり、次回からは筆記試験が再開される)とのことだった。
「筆記試験は無いし、面接試験だけで総合医師のトレーニングプログラムに入れたら儲けもの」と怠け者の虫が騒ぎたて、ぼくは安易に総合医師のプログラムを受験し、合格した。
総合医の詳しい職種内容はこちらの記事を参照いただきたいが、その名前が示すように、総合医は総合的な医療サービスを提供する医師である。つまり、外科、内科、精神科、といった幅広い分野の知識とスキルを持って患者さんに向き合い、より専門的な治療が必要な場合は、専門医に紹介状を書いて患者さんの治療に携わって行く。対象となる患者さんが老若男女であるため、総合医は「ゆりかごから墓場まで(From the cradle to the grave)診る医者」と表現される。長い年月を通じて患者さんと向き合えるという職種はとても魅力的である。
総合医師になる選択を下したぼくは、外科、内科、精神科だけではく、小児科、産婦人科などの知識やスキルも必要であると感じ、Sir Charles Gairdner Hospitalの人事部に、小児科、産婦人科のトレーニングが受けられるようにしてほしいとお願いをした。Sir Charles Gairdner Hospitalには小児科も産婦人科もないため、別の病院と連携してもらう必要があったのだ。
幸い、Sir Charles Gairdner Hospitalの近所に、Perth Children’s Hosptailという小児科病院、そしてKing Edward Memorial Hospitalという産婦人科病院があった。Sir Charles Gairdner Hospitalの人事部は、それぞれの病院にコンタクトを取り、雇用契約を成立させてくれた。
小児科と言っても、外科、内科、精神科など、様々な分野に分かれている。特定の専門分野で働くよりも、ぼくは救急科で働くことを希望した。なぜなら、小児科病院で治療を受けている(ほぼ)すべての子供たちは、まず最初に救急科で診療されるからだ。つまり、小児科すべての症例が集まるのが救急科なのだ。
Perth Children’s Hosptailの救急科で働く医師は、ガイドラインに従って子供たちの診療に当たる。また、お薬は、Australian Medicine Handbook – Children’s Dosing Companionに基づいて子供たちに処方する。もし、これらガイドラインに無い症例に出会ったら、救急の上司に相談したり、専門医の指示を仰ぐようになっていた。
Perth Children’s Hosptailの救急科のお仕事は、コロナウイルスが蔓延していたこともあり、さまざまな呼吸器感染症にかかった子供たちが親御さんに連れられて来た。コロナウイルスは子供はもちろん、クループのせいで犬が吠えるような音の咳をしている女の子、百日咳で呼吸困難に陥った男の子、扁桃周囲膿瘍にかかって物が食べられない少年、など様々な子供たちを診ることができた。
もちろん、感染症だけでなく、フットボール中に鎖骨を骨折した少年、お父さんと遊んでいる最中に腕を引っ張られてひじの関節を脱臼した女の子、椅子から落ちて手首を骨折した女の子、ひどい便秘でおしっこが出なくなった男の子、幽門狭窄症のせいで噴出性嘔吐した幼児、虫垂炎で食事を食べなくなった少年、お父さんを奴隷のように扱う自傷行為を繰り返す少女、口角泡を飛ばしながら「ここから出せぇ!お前なんか殺してやる」と監禁室から母親に叫ぶ全裸の少女、インスリンを過剰摂取し自殺を図った女の子、里親から何度も逃げ出し救急科に助けを求めに来た少女、建設現場で遊んでいたときに機械が頭の上に落ちてきて救急科に運ばれた時には血を吐いて亡くなった少年、など様々な小児科ケースに対応することできた。(そういえば、それ以外にも、子供よりもひどい症状でグタっとしていたコロナウイルスに感染したお母さんをSir Charles Gairdner Hospitalの救急科に送ったこともあったなぁ)
救急小児科の仕事はとても大変で、泣き叫ぶ子供たちだけでなく、うちの子を今すぐ助けてくださいという無言の視線を送る親御さんのケアにも当たらなければならない。医師が親御さんとうまくコミュニケーションが取れていないと、子供たちはそのことを敏感に感じ取り、なおさら恐怖を感じるのだ。