前回の記事『日本の医療、アーユーレディ?日本語が一言もしゃべれない外国人が日本にドッと押し寄せるラグビーワールドカップと東京オリンピック』で、ぼくが日本に帰国していたことをお伝えした。実は、異能vationとUrdocの件以外にも、日本で行なったことがある。
ホリデー気分で東京を心赴くまま散歩していたぼくだが、理科科学研究所・総合脳科学研究センター時代の同僚から突然、日本の大学病院で「臨床英語の伸ばし方」について医学生にセミナーを開いてほしい、と頼まれたのだ。
正直、セミナーを開くことはとても難しい。講演者は、オーディエンスの「英語力(英語で夢を叶える能力)」を把握し、そしてオーディエンスが求めていることをハッキリさせないと、何を講演すればいいのか分からないからだ。
それでも、ラグビーワールドカップや東京オリンピックなどで日本に外国人客がドッと押し寄せる状況に戦々恐々としている医療関係者が「英語で対応できるようになりたい」と感じている事実を、ぼくは無視することが出来なかった。また、日本に来てくれた外国人の方に「日本の医療は最高のケアを提供してくれた」と言ってもらいたいという想いから、ぼくはセミナーを開くことをOKした。
ご招待いただいたのは埼玉医科大学病院、セミナーを開いたのは池田正明先生と中尾啓子先生がいらっしゃる神経科学グループに所属する医学生である。
セミナーを開くことの難しさを理解していたぼくはまず、オーディエンスの医学生がどのようなことを求めているかを聞くことから始めた。医学生が言ったことを正確には覚えていないが、臨床における英語力というよりも、一般的な英語力を伸ばすための方法論を知りたがっている生徒が多かった。それでは、とぼくは英語で夢を叶えるための10のスキルについて話を始めた。
ちなみに、ぼくが提唱する10のスキルは、
01 Vocabulary
02 Sentence (Grammar)
03 Paragraph (Collocations)
04 Chapter (Phrasal verbs)
05 Story (Idioms)
06 Analytical thinking
07 Critical thinking
08 Synoptic thinking
09 Offer solution
10 Raise new issueです。
— ごとうひろみち (@iTELL_) 2018年12月22日
そのままセミナーを進めていたのだが、中尾先生から「医学生が求めているのは一般論ではなく、臨床における英語力をいかにして伸ばすか?ということ」というご指摘があった。正直なところ、この成功の10のスキルが身についている人であれば何をすればいいのか自ずと考えられるんだけどな、と思いながらも、ぼくは医学生が求める「臨床における英語力」が何を指しているのかを聞き始めた。
話し合いをして分かったことはこうだ。日本語ができない外国人患者さんが目の前にいる。その人とどうやって英語でコミュニケーションを取ればいいのか?また、そのコミュニケーション能力を伸ばす効果的な練習方法はないのか?という2点。
臨床における英語コミュニケーション
臨床における英語コミュニケーションには、従来の英語試験が推し量れないスキルが含まれている。それがどんなスキルなのかを解説すると分厚い本ができてしまうので、できるだけ手っ取り早く理解したいという人は次の書籍を読まれたい。
88ページの入門書かつ良書
たとえ、あなたが、英検1級、TOEFL満点、TOEIC満点、IELTS満点、ケンブリッジ試験CPE満点を持っていたとしても、患者さんに「あのお医者(看護師・薬剤師・理学療法士etc)さん、最悪」と言われる可能性は十分にある。このことをまず理解しておかなけばならない。このことを無視して、従来の英語試験の点数を伸ばそうとしても、無駄な努力で終わってしまう。
臨床における英語コミュニケーション能力は非常に大切なスキルである。臨床における英語コミュニケーション能力が患者さんの治療に対する満足度に比例するというデータも沢山あるし、医療従事者自身の仕事に対する満足度とも比例するというデータすらある。公私ともども満足するためにも英語コミュニケーションの正体を理解しておく必要がある。
臨床英語の伸ばし方
臨床における英語コミュニケーション能力の正体が分かったら、実際にどうやってそれを伸ばしていけばいいのかという疑問にたどり着く。この問題は、日本人だけでなくネイティブの医療関係者にも重要な問題であるため、たくさんの論文が存在する。ぜひとも、最新の論文だけでも目を通しておきたい。この論文は簡潔にまとめられていたので、これから始めてもいい。
しかし、日本人の医療関係者が外国人患者さんに出会う頻度は、今のところないそんなに無い。そんな状況で、いかにしてラグビーワールドカップや東京オリンピックでドッと押し寄せてくる外国人患者に備えることができるのか?
ぼくが埼玉医科大学の医学生に教えたことは、次の3つである。
- 日本人同士で臨床英語グループを作ること
- グループ内でOSCEの練習をすること
- 臨床英語力の向上のすべては患者さんのためであることを理解すること
1.日本人同士で臨床英語グループを作ること
まわりに外国人の方がいなくても、臨床英語力を伸ばしたいと考えている日本人同士がグループを作ることはできる。グループを作る際に、外国人の方、臨床英語ができる方がいればベターだが、いなくてもいい。まずはグループを作ることが大切な一歩となる。あなたと他の誰かひとりだけのグループでもいい。何かを始めなければ何も変わらない。
2.グループ内でOSCEの練習をすること
グループができたら何をするのか?OSCEの練習である。OSCEとは Objective Structured Clinical Examinationというもので、簡単に説明すると臨床シナリオ試験である。臨床には、History-taking、Physical Examination、Differential diagnosis、Investigation、Managementという段階に分かれている。それぞれの段階に必要なスキルを練習するのだ。
ぼくが日本の医学生にお勧めした方法は、Geeky Medicsで使われている英語を丸暗記し、グループの誰かに患者さんになってもらい、その英語を飽くなき練習することである。この際、あなたと患者さん以外に、あなたの臨床英語スキルを審査するもう一人の人がいればベターである。あなたのシナリオが終わったら、審査員と患者さんから、あなたの良かった所、改善する点などをフィードバックしてもらおう。
Geeky Medicsの動画サンプル(他にも沢山ある)
また、OSCE書籍が沢山売られているので、どれかを使い練習を重ねることである。OSCE書籍には、審査用の採点表がついているので、どのような部分が重要なのかを知る意味でもぜひとも購入したい。何度も練習することで、自分がよく忘れてしまう部分も明らかになる。ぼくが個人的に良かったと思った書籍はこちら。現実の臨床シナリオと比べればシンプルすぎるかもしれないが、まずはシンプルなものから始めることが複雑なものを理解するうえで重要になる。
ぼくが紹介した練習方法は、臨床英語を伸ばすのにとても効果的である。医療関係者としてだけではなく、患者さんや審査員の役割を果たすことで、患者としての気持ちが分かり、他の人の臨床スキルを客観的に見ることで自分がどのように臨床英語を伸ばせばいいのかということをハッキリさせることができる。臨床英語グループを今すぐ作ってOSCEの練習をしてほしい。
3.臨床英語力の向上のすべては患者さんのためであることを理解すること
もちろん、すべての医療シナリオをOSCEで練習することはできない。でも、臨床英語を伸ばしたいのであれば、どこからか始めなければならない。ぼくはOSCEを勧めたが、別のやり方でもいい。ただ、どこから始めるにせよ、日本の医療関係者には「外国人患者に最善のケアを提供するため」という共通のゴールがあることを覚えておいてほしい。そして、共通のゴールがあるグループはとんでもない結果を生みだすことが出来る、ということも知っておいてほしい。
この記事を読んで臨床英語を磨くためにグループを作った人は、自分の英語力の無さに絶望したり、拙い英語で大きな恥をかくかもしれない。でも、すべては患者さんのため、だということを忘れてはならない。患者さんの命は、あなたの絶望や恥よりも重いのだ。
謝辞
セミナーに招待してくれた元同僚のPavel Prosselkovさん、埼玉医科大学の池田正明先生ならびに中尾啓子先生、そして埼玉医科大学の学生さん、どうもありがとうございました。日本の医療関係者の臨床英語力の向上の一助になれたならこれ幸いです。



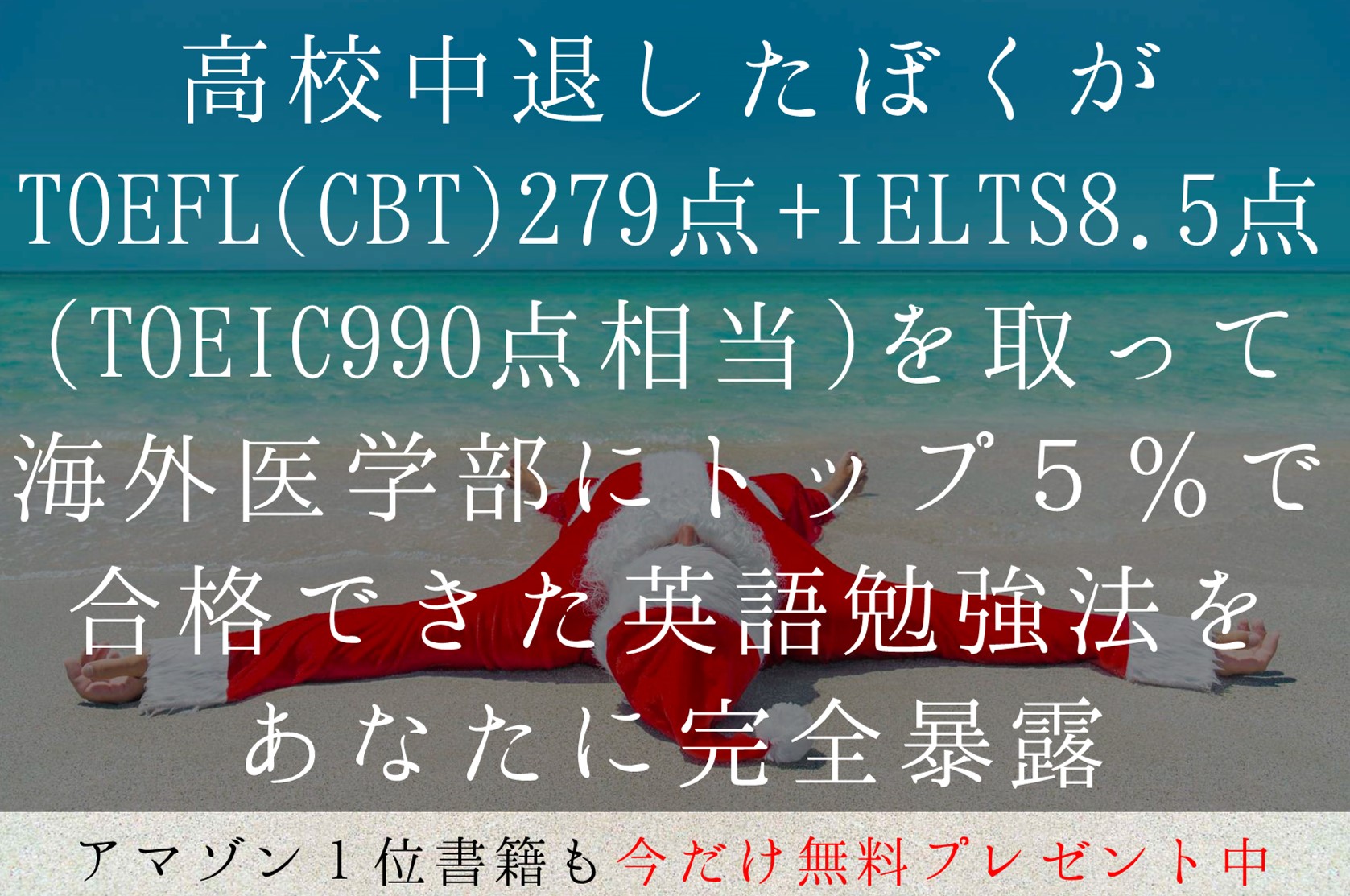
先日は有り難うございます。
対象は医学部1,2年生で「英語で夢を叶える方法」という一般的な聴衆なら大変興味を持たれるお話なのに方向転換をお願いしてしまい失礼いたしました。学生さん達は既に医学部に入学し、目標に向かって歩み始めております。個人的に興味を持ったのはオーストラリアの医学部入学に特に基礎教養科目の修得を必要としていないと言うことです。臨床実習が3年生から始まりますので、実際に現場に出れば必要なことが何かも分かってくると思います。今後とも埼玉医大の学生さん達に色々アドバイス頂ければ幸いです。
中尾先生、コメントありがとうございます。また、セミナーに招待していただいたこと心から感謝しております。
ぼくの個人的な考えだと、オーストラリアの医学部は、知識を持つ人ではなく、考える能力が高い人を求めています(知識と思考は排他的ではないですが、必ずしも比例するわけでもありません)。インターネットを使えば簡単に知識にアクセスできる今の時代において「自分で考える力」が重視されているのではないかと思います。
日本の医学生の英語力がどれぐらいなのか分からないのですが、先生がおっしゃていた「日本の医学生はすでに高い英語力を持っている」という言葉に懐疑的です。というのも、理研で出会った様々な高学歴の人たちでさえ英語での意思疎通に苦戦している姿を見てきたからです。ツイッターでも書いたのですが、「日本の医学生の英語力が高いのかどうか」を測るひとつの指標として、アメリカの医学部入学試験MCATのVerbal Reasoning (最近では名前がCritical Analysis and Reasoning Skillsになったようです)を使ってどれぐらいの成績が取れるのかを見て評価してみるのもありかと思います。最後に、誤解のないように補足しておくと、ぼくが考える英語力とは「英語で夢を叶える能力」のことであり、「TOEIC満点」などの枝葉的なものではありません。
早速御返信頂き恐縮です(100文字制限があり余り記載できませんが)。基礎教養科目によって得られるのは単なる知識ではなく考え方の基盤です。フーリエ変換を知らずにMRIの画像が読めるはずがありません。また医学部生にとっては英語は手段であって目的ではありません。故に「”英語で”夢を叶える」という考え方は少なくとも既に医学部に入学し、各が理想とする医師像に向かって進み始めている学生さんには若干違和感のある概念です。意思疎通に苦戦するのは母国語でない以上当然だと思いますし、だからといってこれまでの英語教育が役に立っていないとは思えません。いろいろな立場の方がいて議論が深まるとは思いますが、今回のセミナーでお願いしたかったのは英語を目的とする勉強の仕方や日本の医学教育批判を聞くことではありませんでした。
中尾先生、「英語で夢を叶える」の「英語で」の部分は英語がツールであること意味しています。そのため、英語をツールとして使いながら理想とする医師像に向かう医学生にとってこのスキルを知ることは決して無意味なことではないと想像します。ぼくが取り組んでいるのは「ツールとしての英語」を様々な人間活動においてどう磨くか、という問題です。これはぼくの仮説にすぎませんが、分野に関わらず英語を使って仕事ができる人(医学なら医学、ビジネスならビジネス、芸術なら芸術)には何か共通点のようなものがあります。できるだけ掘り下げてみたら、10のスキルにたどり着きました。これらは言ってしまえば当たり前のスキルですが、身に付けるのに長い年月(と習熟を目的とした訓練)が必要です。このスキルが身に付いていれば、ぼくがアドバイスしたようなことは医学生自らが考えられたと思います。老子の言葉に(本人は言ってねぇというかもしれませんが)、Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.という言葉があります。学生に魚を与えることを求めた先生に対し、ぼくが魚釣りを教えようとしたために食い違いが起きたのではないかと思います。フーリエ変換・・・オーストラリアの医学部では学びませんでした。学んだのは、MRI技師が書いたレポートを読んで、画像と照らし合わせて、それが正しいのかどうかを判断する訓練ぐらいでした。頑張って勉強を続けます。あと、字数制限を10,000文字に変更しておきました!
私は学生に魚を与えて欲しいと思ってもいませんしそうした依頼もしておりません。
そもそも、彼らがどうすれば彼らにとって必要な英語力を身につけるかを、必要な場面が来ればわかることで、将来的に理解できないとも思っておりません。
今回のセミナーは公式なものではなく、Pavelさんに非常勤講師として英語で神経科学の講義をお願いしていたところごとうさんを友人として紹介されたので、日頃海外の医療制度に興味を持っているかもしれない学生さんとの対談会をお願いしたところ御自身がおっしゃったようにいきなり企業宣伝のような講演が始まったので、正直学生さんの教育目的に合わないと思って方針変更をお願いしたのです。本質は細部に宿ると言いますので、仮に原則論に同意できなくても具体例の中にまなぶべきものもあるかもしれないと具体的なお話に変更して頂きました。
元々日本の高校教育を離脱され、オーストラリアに飛び込んである意味他の高校生が体験されていないことを実践された経験談の中にもしかしたら何か学べるものがあるのかと興味を持っただけです。そうした経験を経てこれからどのような医師として活躍されるのか抱負もお聞きしたかったですが、、、、
基本的には、医学部生に取って単なる手段である英語を学ぶために実践を積む以上に時間を掛ける必要などないと思います。若いうちに留学すればあっという間にあちらで普通に生活し研究できるようにもなります。
それ以外に今の医学部生には医学部生でなくてはできない勉強なり、テーマがあります。どれにそれくらい時間を掛けるべきかはそれぞれの学生さんの思い描く理想の中で決めるべき事だと思います。
実際、私が前勤務地の大学で医学研究を指導した学生さんの中で海外での活動を目指して留学し、アメリカで立派に医師として活動されてる方もおります。
また、アメリカで医師をするならアメリカの資格は必要ですが、日本で医師として活動するのに不要な資格を取る意味は無いと思います。ましてや神経科学を勉強された後藤さんなら御存じのようにある年齢を超えて習得した言語はネィテイブスピーカートは異なるものです。それでも医学研究や臨床医学で貢献できるのであれば目的はかなうと言うことではないでしょうか?
私は、あのセミナーの後で本来自分たちには無関係な部分にも寛大に耳を傾け、オーストラリアの医学教育でごとうさんが用いられた本を紹介して頂いたこと、グループで勉強するというアイディはうちの大学の教育の中でも実際に行われていることで、すぐに実践しようと言う発言が出たその積極性に対してうちの学生さんを誇りに思います。
いろいろな考え方をする方がいらして、必ずしも合わない部分があっても少しでもプラスを抽出しようとするその部分をです。
また、基礎医学しか学んでいない学生さんが、医療の場でどのような能力が必要になるか具体的に想像できないことは学生さんに理解する能力ないわけではないですし、我々教員もそう考えてはいないことだけはお伝えしたいと思います。これからの日本の医学を担う能力とやる気を持った素晴らしい学生さんだと思っております。
いずれにしても、どのようなことをお聞きしたいかを非公式な対談会とは言え文書で詰めておかなかった私のミスですのでその点は深くお詫び申し上げます。
その場で学生さんの意見を聞いてから始めたセミナーだったのですが、こちらがその意見を十分に理解できていなかったのかと残念に思います。改めて即興セミナーすることの難しさを痛感しました。自分たちには無関係な部分にも寛大に耳を傾けてくれた学生さんたち、そして既知の勉強法の議論に時間を割いてくれた先生に感謝します。すべては患者さんのためになれば幸いです。