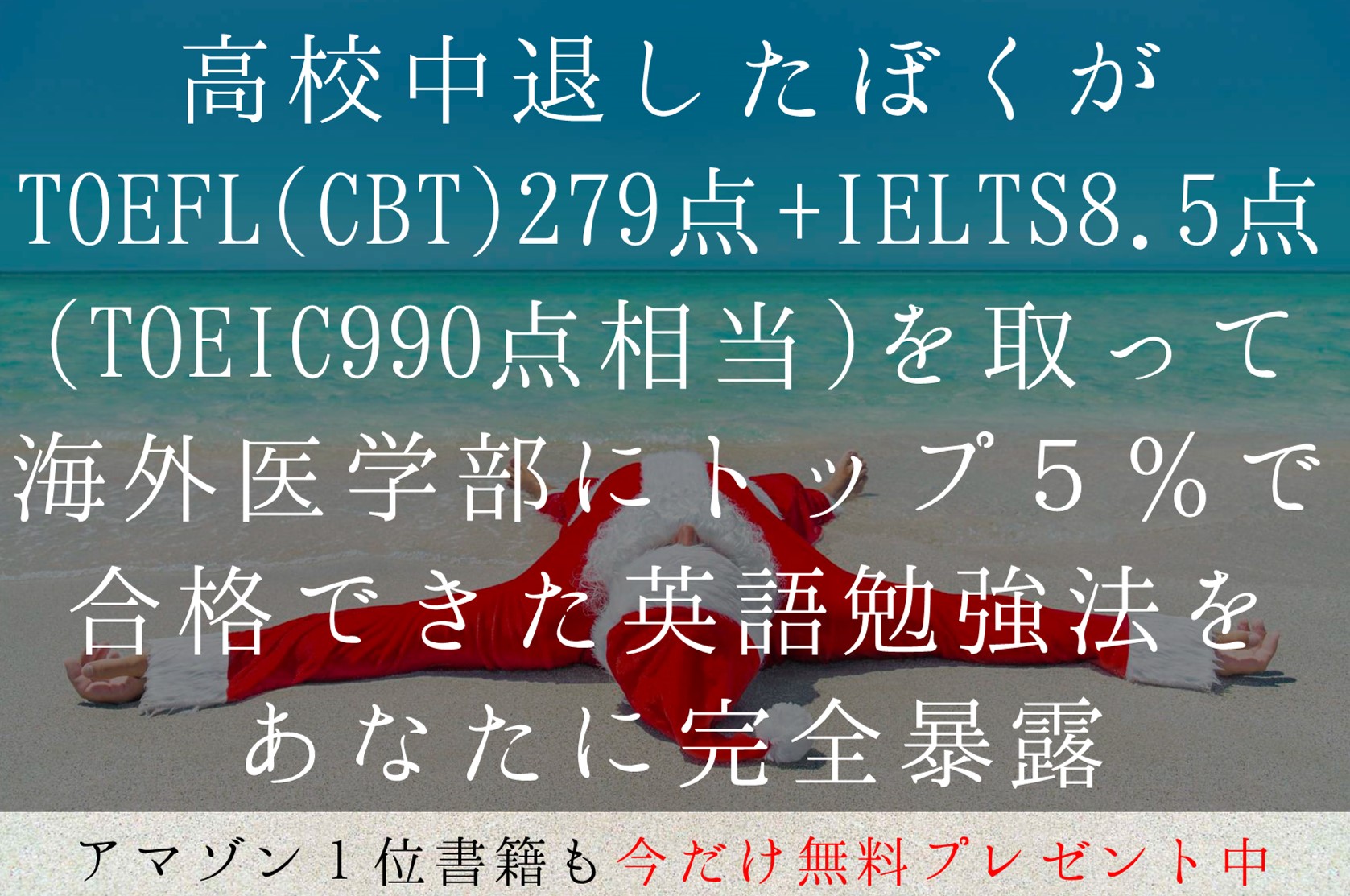この記事では、
神経科学の発展スピードについて、
個人的な感想を述べたい。
ぼくは西オーストラリア大学で神経科学を専攻し、
ぼくが行動遺伝技術開発チームで働いていたときに
感動した技術がある。
それは、光遺伝学(Optogenetics)と呼ばれるもので、
簡単に説明すると、細胞に遺伝子改変を行い、
光を使ってその遺伝子(またはタンパク質)を
ON にしたり OFF にしたりする技術である。
この技術は神経科学の分野で幅広く適用され、
さまざまなエキサイティングな研究結果が世界で報告され、
2010年にはネイチャーメソッドの
「メソッド・オブ・ザ・イヤー」に選ばれている。
Optogeneticsの欠点は、
遺伝子改変を行なった細胞に
光を物理的に照射しなければならないところにある。
たとえば、脳の内側に位置する視床(Thalamus)の細胞を
Optogenetics を使って制御しようとすると、
光は頭蓋骨を貫通しないため、
光ファイバーを視床(Thalamus)まで物理的に持ってくる必要がある。
その過程において、
脳表面から視床(Thalamus)までの
細胞を破壊しなければならない。
脳機能の多くはネットワークの産物であるため、
あるパーツを破壊してから、
別のパーツの働きを研究することは、
光遺伝学が持つ大きな欠点だった。
行動遺伝のメンバーとこの欠点について議論したとき、
「磁場」を使うことでこの欠点が解消されることは
(磁場は頭蓋骨を傷付けずにあっさりと貫通する)
誰の目から見ても明らかだった。
ぼくらはまだ実現もしていない、
磁場を使って遺伝子の ON と OFF を操作する技術を
磁気遺伝学 (Magnetogenetics) と勝手に名づけた。
そして、Nature 誌でその名前が採用された・・・わけではない。
たまたま同じだっただけである。
あれから数年の間に、
磁気遺伝学の実現につながりそうな論文がちらほら出始めた。
そして、あの他愛の無い議論から約6年後、
Nature Neuroscience に
『Genetically targeted magnetic control of the nervous system』
という論文が発表された。
磁気遺伝学(Magnetogenetics)の
日の出を象徴するような研究である。
Optogenetics から Magnetogenetics への発展についてふと思ったのは、
研究者がある科学的好奇心を持つと、
その技術は5,6年で日の目を見るのではないかということだ。
もちろん、好奇心がつねに実りにつながるわけではない。
ただ、必然性のある技術はおそらく
5,6年で実現するのではないだろうか?
研究に取り組む大学生・大学院生・研究員の皆さん、
あなたの研究もこれからの科学を大きく変える、
必然性のあるものかもしれません。
応援しています。

 出典:
出典: