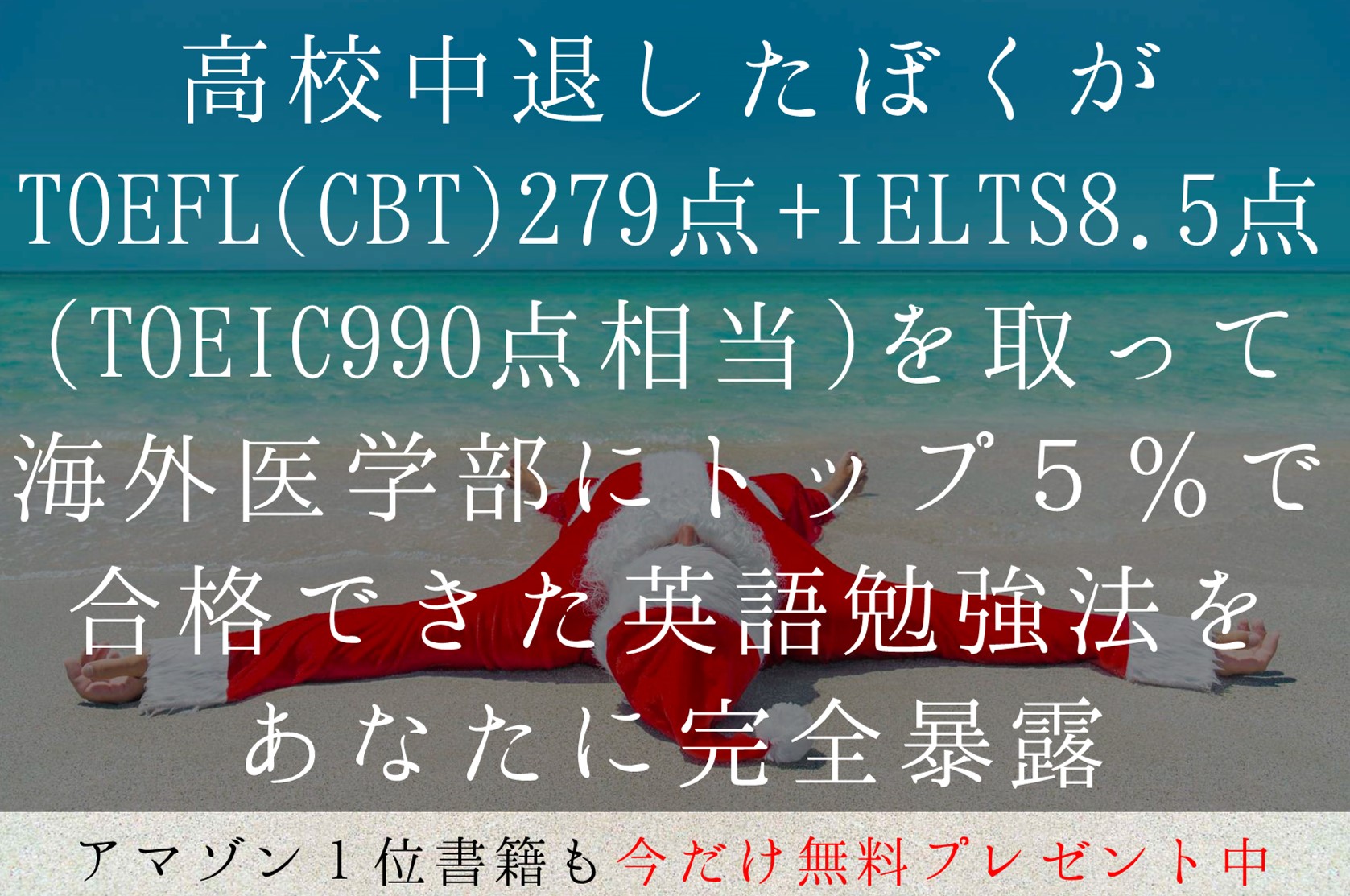尊敬理由(1)だれよりも先に仕事を始める
ぼくの生まれて初めてのアルバイトは、
新聞配達だった。
新聞配達の仕事をやっていた
中学校の友人の誘いで始めたのがきっかけだ。
朝5時ぐらいに新聞販売店に出社し、
まず新聞にちらし広告をはさむ作業をする。
広告をはさみ終えると、
新聞を配る順番に並べ替える。
ぼくが住んでいた福岡は、
90%以上が西日本新聞をとっていたので、
新聞社の順番で混乱することはまず無かった。
新聞を並べ終えると、
新聞を自転車の前かごと後ろ荷台に載せていく。
配達中にかごと荷台から
取り出しやすいように
積み上げていくのがコツだ。
すべての新聞を載せ終わると、
あとは自転車をこいで、
配達先へと移動していく。
配達の順番は、
ベテランの新聞配達員に地図を渡され、
このルートでくばると
効率的に配達できるよと教えられる。
最初の頃は、
地図を見ながら自転車をこいで配達する。
尊敬理由(2)体力的に大変な仕事である
新聞配達をしたことがある人なら分かると思うが、
大量の新聞を自転車に載せると、
自転車がブルブルと震える。
ほんとうにブルブルと震えるのだ。
自転車のハンドルが
震源地にでもなったかのように
小刻みにゆれる。
ぼくが新聞配達をしていた頃は、
マンションの1階にある郵便受けではなく、
各部屋のドアの郵便受けに直接配達していた。
最近では、
1階の入り口にセキュリティドアがある
マンションが多いので、
あまりないのかもしれないが、
新聞を数部抱えたままマンションを
1階から8階まで登ったり降りたりすると
とても疲れる。
新聞がしたたる汗に
汚れないようにしなければならない。
尊敬理由(3)つらいこともある
新聞配達のつらさは、
季節・天気に大きく左右される。
大雨や大雪の日は、
自転車での新聞配達のつらさが
2倍にも3倍にもなる。
ぼくは大雪のときに配達をして、
凍りついたアスファルトに転んだことがある。
外は真っ暗のなかで、
落とした新聞を拾い集め、
かごと荷台に積みなおす作業は、
心細くてとても寂しいものだった。
幸い、
新聞はビニール袋に入れてあったので
新聞配達そのものに支障は無かった。
ぼくは新聞配達のつらさを克服できずに、
アルバイトを短期間でやめてしまった。
ぼくの友人は、
中学卒業まで新聞配達を
継続したのではないかと思う。
新聞配達は
とてもとても大変な仕事です。
新聞配達員さん、ご苦労様です。敬礼。

 出典:
出典: